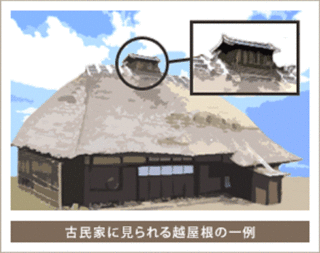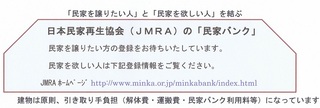日本の民家は高温多湿の夏を工夫と知恵で乗り切っていました。
カッコよく言えば自然エネルギーを利用したパッシブ建築です。
今日は、民家の「空気を流す機能」について
民家の屋根には、越屋根と呼ばれる天窓に似た窓がよく見られます。
越屋根から煙や暖まった空気を外に出すことで、室内に新鮮な空気が入り込
み、それが風の流れとなりました。
シンプルですが、理に叶った夏涼しくくらす工夫といったところでしょうか。
写真がなく、YKKapさんの サッシカタログより抜粋

しました。<m(__)m>
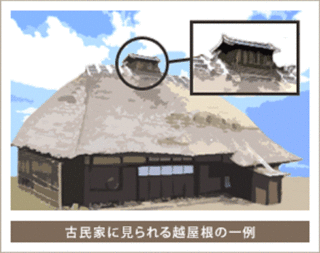
これなんかも、高低差のある窓の組み合わせ


空気を流す機能とは、最下部の空気の取り入れ口と、最上部の排出口までの高さ方向の距離と排出口の大きさを考えることです。
この時、取り入れ窓と排出窓との高低差は大きければ大きいほど空気の流れが大きくなります。
室内では欄間がその機能を担う部位です。
下の写真は金原明善生家 です。
民家の間取りは開放的に作られていますが、それでもなお、高さは低くても、風と明かりを取り込みたいというあらわれでしょうか。

ではこの辺で
続きは次回に
千年杉建築事務所 小林正幸
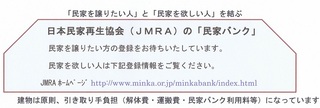

 住宅| 中央区 (旧西区)|
住宅| 中央区 (旧西区)|  しました。<m(__)m>
しました。<m(__)m>